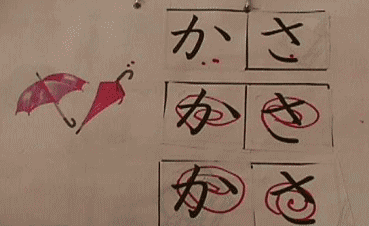| 題材 | 授業の流れ | ||||
| 平成16年度の文集 | 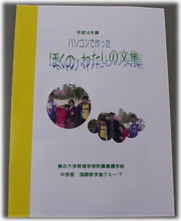 表紙の写真は私と生徒達、いつも教えに来てくれた学生のIさんと子ども達の2枚です。 表紙の写真は私と生徒達、いつも教えに来てくれた学生のIさんと子ども達の2枚です。中には、生徒が入力した作文と私が選んで貼った画像があります。 生徒の言葉を生かしているので、とっても楽しい文章で、中には笑える文章もあります。 (3月22日) |
||||
| お金そろばん | 今日の国語・数学では作成したお金の教材を使った。 「お金そろばん」といいます。  おわかりのように5円、50円、500円が上の段にあります。 もし5をよく理解していない子どもの場合は1円を10こ並べていきます。 今日は最初に1円からずっと並べていき、1万円まで並べました。 中学生の場合、1000円札を使うことも多いので、一応札も知って欲しかったのです。 その後に、10円玉と100円玉を使って「30円」「70円」「400円」などと並べる学習をしました。 実は2人の男の子はお金はかなり理解しているのです。 女の子のために、この教材を作ってみました。 でも、このそろばんを使うと、みんなお金の大きさを理解しやすいように思います。 今日気づいたことは・・・ 「3びゃくえん」「5ひゃくえん」「6ぴゃくえん」と「百」の読み方が変わるのは大変理解しにくいのです。 女のこは「3・・・」と言ったきり「百」が出てきません。 そういえば男の子場合も「百」を言わないのです。 やはり「ひゃく」というのか、「びゃく」というのか「ぴゃく」というのかがややこしいからかもしれません。 私たちは何気なく使っている「百」の読み方も、こんなに難しいのですね。 しばらく練習して慣れてもらうしかないかもしれません。 後半は女の子は学生のIさんと一緒に「+2」の練習をしました。 もう指を使わなくてもできるようになりました。 こんどは「+3」をしていくことになります。 少しずつ学習していくことで、分かるようになり、自信がついてきています。 |
||||
| タイルで「5+2」その2 | 国語・数学の時間にI先生が新しい足し算の教材を持ってきて女の子に教えた。 この教材はその1とは少し違いますね。 原理は同じです。 子どもが分かりやすい方を選ぶといいのでしょう。 この教材で+2を学び、女の子はずいぶん上手になってきました。 もう指を出して数えなくても、頭の中でイメージしながら答えが出るようになりました。 (12月25火) |
||||
| タイルで「5+2」その1 | 国語・数学では学生のIさんが女の子に「5+2」などを教えました。 タイルでできた教材を使います。 下のようにタイルを重ねたものが1〜10まで並んでいます。 今日は「+2」を教えます。 「3+2」はの場合3のタイルの上に2のタイルをのせます。 その後、板を置くと、高さが5のところに一致することを知り、答えが5だとわかります。 女の子は先日このやり方で習った「+1」はできるようになりました。 今日は「+2」ができるようになったのですが、まだ確実にと言う訳にはいきません。 じっくりやっていくそうです。 なんでこんなややこしいことをするのか? 子どもの中には指をだして3+2などを解く子がいます。 でも、これでは6+○や8+○はできません。指が足りないから・・・。 そこで数を量としてしっかり理解させる必要があるのです。 小さい頃からこういうやり方で数を理解していると、後になって数の問題が考えやすいのです。 (12月17 金) |
||||
| 文字カードを貼る | 若い女の先生がクラスの子どもに宿題を出してくれます。 国語・数学のグループで教えているので、その子に合った宿題を出してくれるのです。 その子はお話は上手なのですが、ひらがなを書くことを目下勉強中。 自分の名前は書くことができます。 もっと多くの字が読めるように、書けるようにと、こんな宿題を出しています。 下の画像のように、かさの絵を見て「か」「さ」のカードを正しく貼るという宿題です。 「か」の字や「さ」の字の正しい置き方を考え、のりで貼ってくるのです。 毎日いろんな単語の文字を楽しみながら貼ってきています。 書くことも大切だし、このように貼る操作を通して学ぶのもおもしろいものかもしれません。 「○」をもらうことがうれしくて、毎日やってきています。 (12月15 水)
|
||||
| 促音の勉強 数学のグループ |
久しぶりの国数の授業に、学生のIさんが来てくれた。 流れは 1 先日書いた「すずかけ祭り」の作文を読む。 2 国語は促音の勉強。 ここのプリントをカードにして、促音の単語を読む。 このプリントに書いていく。 このテストプリントを解く。 3人の生徒はよくできました。 3 数学は 2人の生徒は2けた、3けたの引き算をする。文章題をする。 女の子はIさんと1桁のものを数えたり、簡単な足し算をしたりする。 女の子の段階と男の子の段階は少し違います。 Iさんが女の子を個別にみてくれるので助かります。 次の時間には、女の子に教材を作って6以上の数の足し算を教えるそうです。 女の子は指を出して足し算をしているのですが、6以上だと指が足りなくなるから難しいようで、このあたりをIさんが指導してくれます。 知的障害のある子どもの算数では、この段階の指導は難しくておもしろい部分でしょう。 (12月1日 水) |
||||
| 10円玉、100円玉 | 今、国数ではお金の勉強をしています。 きこさんは10円玉、100円玉だけだと数えて「いくら」が分かりますが、金種が二つになるととまどうようです。 そこでいつも一緒に教えてくれる学生のIさんがこんなプリントを作りました。 これで110円、120円をゆっくりと理解してくれるでしょう。 私たちにとっては当たり前のようなことでも、子どもにとって抽象的な硬貨というものは分かりにくいものです。 まして10円玉が10個集まると100円玉になるということはなかなか理解しにくいものでしょう。 このあたりを理解してもらえるような指導法や教材をIさんが工夫してくれています。 (10月11日 月) |
||||
| 学生とお金の学習 | 今日から国語・数学の授業に熊大の障害児教育科の学生も参加してくれることになった。 これは「大学との連携」という研究テーマの推進の一環として始めました。 今日は3人の学生が参加し、そのうちの一人Iさん(男性)が私のグループに入ってくれた。 まず数学ではお金の学習。 今日は手始めに硬貨の金種の弁別と、「ぜんぶでいくら・おなじきんしゅ」をした。 3人の生徒のうち一人が「10円が3つならんでいくらか?」「100円が5つならんでいくらか?」の問題が苦手であった。 そこでI先生に個別に教えてもらった。 ゆっくり教えていくうちにだんだん理解できて100点が取れたようだ。 その間、私は2人の男の子に3たくクイズをしてもらった。 「90点とれた!」などと意欲的にやっていた。 後半はパソコンでの作文。 今回は「夏休みのこと」がテーマです。 学生さんが入ってくれたおかげで、子どももよく理解できたと思う。 (9月15日 水) |
||||